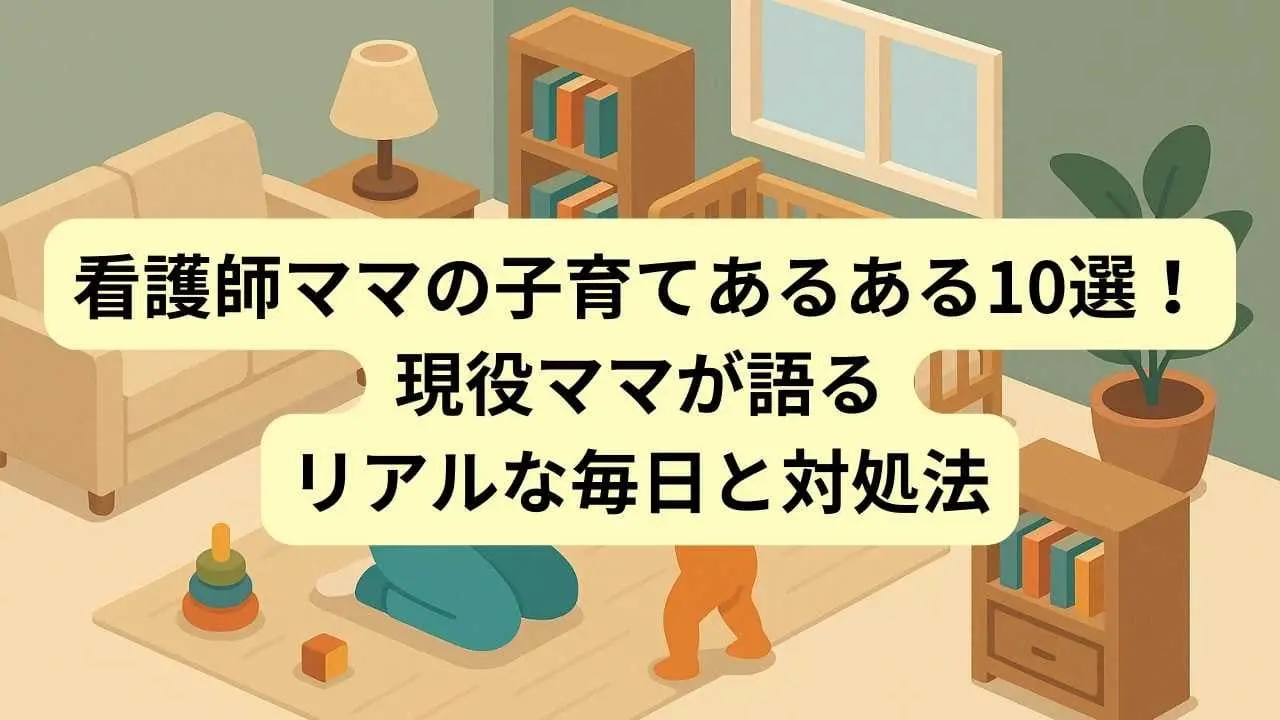看護師として働きながら子育ても頑張る――。
それは決して簡単なことではありません。
昼夜問わず働くシフト制、急な呼び出し、患者対応の緊張感…。
そんな日常の中でも、我が子の笑顔を見ると「よし、もうひと頑張り」と踏ん張れる。
でもその裏側には、疲労、葛藤、罪悪感など、言葉にしにくい感情もたくさんありますよね。
この記事では、現役の看護師ママたちが感じている「子育てあるある」10選をご紹介します。
「分かる…!」と共感できるエピソードはもちろん、忙しい中でも前向きに乗り切るちょっとした工夫や対処法もお伝えします。
少しでも、同じ立場のママたちの気持ちが軽くなりますように。
看護師ママの子育てあるある10選
看護師ママの子育てあるある10選についてご紹介します。
1. 夜勤明けでも育児は待ったなし
夜勤明けにヘトヘトで帰宅しても、「ママ~!」と元気いっぱいに迎えてくれる子ども。
もちろんうれしいけれど、本音は「ちょっとだけ寝かせて…」という気持ちもありますよね。
睡眠不足の体にムチを打って遊び相手をしたり、ごはんを作ったり、寝かしつけたり。
看護師という職業柄、「休憩=完全オフ」が取りづらい生活だからこそ、育児との両立は本当に過酷です。
対処法のヒント
・夜勤明けの日は、あらかじめ「何もしない日」と決めておく
・パートナーや家族に「寝る時間の確保」を協力してもらう
・子どもと一緒に昼寝して“同時充電”を意識する
2. 白衣から私服、そしてエプロンに“秒で変身”
病院では清潔感ある白衣を着こなしているのに、家に帰ればエプロン姿で炊事に育児。
勤務と家庭のギャップが激しすぎて、「自分っていったい何役やってるの?」と笑ってしまうことも。
「今日の夕飯どうしよう」「洗濯回さなきゃ」と頭の中はフル稼働。
まるでスーパーヒーローのように、瞬時に役割を切り替える毎日です。
対処法のヒント
・制服や私服を“着替えやすい順”に整えておく
・ワンオペが確定している日は、作り置き&宅配を上手に活用
・エプロン姿でも「がんばってる自分」に心の中で拍手を!
3. 休みなのに保育園の連絡帳チェックが日課
「今日は休み!」と気を抜いているつもりでも、つい保育園の連絡帳アプリを開いてしまう…。
これは“看護師ママあるある”の中でも、地味に多い共感ポイントです。
保育園からの「○○ちゃん、ちょっとお腹ゆるめです」などの報告に反応して、「それはウイルス性かも?」「食事の影響かな?」とすぐ医療モードに入ってしまうことも。
対処法のヒント
・休みの日は、通知オフや“見る時間を決める”工夫を
・医療職だからこそ、冷静な視点と親としての心の余裕を両立させて
・判断が難しいときは、園や小児科に迷わず相談
4. 医療知識が仇になる?ちょっとの熱でも心配しすぎる
看護師だからこそ、体調の変化に敏感。
わが子が熱を出すと、「インフルかも?」「RSウイルスだったら…」とつい重症例を想像してしまい、
過剰に心配してしまうこと、ありませんか?
医療知識があるからこそ、「知らないフリ」ができないのがつらいところ。
ただの風邪でも、不安がどんどん膨らんでしまうのは、職業病とも言えるかもしれません。
 看護師ママ
看護師ママ逆に「これくらいなら寝てればだいじょうぶね」と大雑把に対処してしまうこともあるあるですよ。
対処法のヒント
・まずは親としての直感を信じること
・症状のチェックは冷静に事実ベースで
・必要以上に検索せず、迷ったらかかりつけ医へ
5. つい子どもに処置っぽいことをしてしまう
鼻水が出ていたら吸引、傷ができていたら消毒とガーゼ…。
ついつい自分の職場感覚で“即座に処置”してしまうのも、看護師ママのあるある。
もちろん我が子の健康を守りたいからこそですが、子どもからは「ママ、やりすぎ…」なんて顔をされてしまうことも。
対処法のヒント
・医療行為は「必要最小限」「子どもの心を優先」が基本
・処置よりも「痛かったね」「がんばったね」の声かけを大切に
・時にはおままごと気分で楽しくケアする工夫も◎
6. 子どもに「ママ、今日お休み?」と聞かれる切なさ
朝、「ママ、お仕事?」「今日はいる?」と聞かれるたびに、胸がキュッと締め付けられるような思いをする看護師ママは多いです。
シフト制の仕事だから、土日も祝日も関係ない。
保育園の行事や家族イベントと勤務がかぶることも珍しくありません。
「一緒にいたい」気持ちに応えてあげられないと、罪悪感に押しつぶされそうになることも。
対処法のヒント
・「一緒に過ごせる日」を事前に伝えて、見通しを持たせる
・特別なことをしなくても、“一緒の時間”を大切にする
・子どもと一緒に“シフト表カレンダー”を作ってみるのも効果的
7. 職場の急なシフト変更と保育園調整の板挟み
「明日、代われる?」――そんな一言に、看護師ママは慌てて保育園や家族の予定を確認。
急なシフト変更は医療現場ではよくあること。でも、子育て中のママにとっては一大事です。
保育園の延長保育の有無、パートナーの帰宅時間、家族のサポート体制…。
あらゆる条件が揃わなければ「出勤できません」と言わざるを得ない、苦しい選択になることもあります。
対処法のヒント
・普段から保育園や家族に“万が一”の共有をしておく
・シフト管理アプリやLINEで素早く連携できる体制を作る
・「子育て中であること」を職場にしっかり伝えておく勇気も必要
8. 病院でも家でも“人の世話”で自分の時間ゼロ
仕事中は患者さんのケア、自宅に帰れば子どもと家族の世話。
ふと気づけば、「自分のための時間なんて1秒もなかった」という日も。
美容院もマッサージも、ひとりでゆっくりご飯を食べることさえ遠い夢に感じてしまう…。
そんな日常の積み重ねに、気づかぬうちに疲れが限界を超えてしまうこともあります。
対処法のヒント
・1日5分でもいいから「自分の時間」を意識的に確保
・週に一度でも“自分優先DAY”を設定
・「疲れた」「休みたい」と声に出すだけでも気持ちは違う
9. 子どもが“なんちゃって看護師”ごっこを始める
注射器のおもちゃで「チクっとしますね〜」と言ってくる子どもに思わず笑顔。
看護師ママの働く姿を見て育った子は、ごっこ遊びにもリアルな要素が満載です。
聴診器をあてる仕草や、バンソウコウを丁寧に貼る様子には、ママの影響が色濃く現れます。
大変な日々でも、こうした瞬間に「ちゃんと見てくれてたんだな」と癒されることも。
対処法のヒント(というより嬉しい効果)
・看護師という仕事をポジティブに伝えるチャンスに
・「ママみたいになりたい」という気持ちを素直に受け止める
・一緒に遊びながら安心やケアの心も育てていく
10. 「なんでママだけいないの?」と責められて泣きそうになる夜
家族でのイベントや寝かしつけの時間に、ママだけが不在。
「なんでママいないの?」「ママがよかった…」という子どもの言葉に、胸が締めつけられる夜もあります。
誰のせいでもないと分かっていても、「私がもっと普通の仕事だったら…」と自分を責めたくなる瞬間も。
それでも、仕事を通じて誰かの命や生活を守っている。
その姿を、子どももきっといつか分かってくれるはずです。
対処法のヒント
・「ママはお仕事がんばってるよ」と分かりやすく説明
・帰宅後には、ぎゅっと抱きしめる時間を大切に
・“愛情の質”でカバーできることはたくさんある
看護師ママが実践する子育ての工夫と対処法
忙しくても、夜勤明けでも、看護師ママは子育てを手抜きできない。
でも、完璧を目指す必要はありません。
多くのママたちが実践している「うまく乗り切るための工夫」をいくつか紹介します。
1. 夜勤明けでも無理しない!「できることだけ」のルール
夜勤明けは、体力も気力も限界。
「家事は完璧にやらなきゃ」と思わず、“やらなくていいことはやらない”というマイルールを持つことが大切です。
例えば――
・掃除は最低限、週末にまとめてやる
・ごはんはレトルトや冷凍食品でOK
・育児も「抱っこだけして一緒にゴロゴロ」でも十分
頑張りすぎないことも、立派なスキルです。
2. 夫・祖父母との連携は最強の育児チーム
看護師の勤務は不規則だからこそ、「助けを求める力」も大切です。
夫や祖父母と役割分担を話し合い、「自分が休める時間」を作ることが継続のカギになります。
・連絡手段を統一(LINEグループなど)して、スケジュールを共有
・「○曜日の朝は夫が担当」「○日は祖父母に送り迎え」など役割を見えるように可視化
・感謝の言葉や「ありがとう」を忘れずに伝えることが、長く続く秘訣です
3. 医療知識を活かす!子どもの体調管理テク
看護師ならではの視点は、子育てでも大いに役立ちます。
熱や咳、湿疹などの初期対応ができるのは、強みであり安心感にもつながります。
・体温の推移を簡単に記録できるアプリを活用
・“危ない兆候”と“心配しなくていい症状”の見極めをマスター
・「親としての直感」も忘れずに大切にする
4. タイムスケジュールを整えるアプリ活用術
分刻みで動く看護師ママにとって、スケジュール管理は生命線。
今は便利なアプリがたくさんあるので、上手に活用しましょう。
おすすめ活用法
・家族の予定共有に「TimeTree」などのカレンダーアプリ
・献立&買い物管理に「トクバイ」「クラシル」などのレシピアプリ
・シフト管理には看護師専用の「ナスカレ」「シフオプ」も便利
“見える化”することで、無駄な焦りやすれ違いを減らすことができます。
看護師ママの子育てに関するよくある質問(FAQ)
看護師ママの子育てに関するよくある質問についてまとめました。
Q1. 看護師ママは本当に育児と仕事の両立ができるの?
シフト制の仕事は大変ですが、家庭の協力やスケジュール管理アプリの活用、パート勤務や夜勤免除などの選択肢をうまく使えば、両立は可能です。
「完璧を目指さない」ことも大切なポイントです。
Q2. 看護師ママの1日はどんなスケジュールですか?
夜勤・日勤によって異なりますが、家事・育児・仕事を分単位で回す忙しい日々です。
家族の協力や「時短グッズ」「作り置き」などの工夫で、時間にゆとりを作っている方も多いです。
Q3. 看護師としての知識は育児に役立つ?
はい、非常に役立ちます。
発熱や怪我への対応などで冷静な判断ができるのは大きな強みです。
ただし、心配しすぎてしまうというデメリットもあるため、「親としての目線」も忘れないようにすることが大切です。
Q4. 子どもに寂しい思いをさせていないか心配です。
その気持ちは多くのママが抱えています。
大切なのは「一緒にいる時間の質」。短い時間でもしっかり向き合えば、子どもはしっかり愛情を感じてくれます。
シフトを可視化するカレンダーもおすすめです。
Q5. 看護師ママだからこそできる子育ての工夫はありますか?
例えば、医療知識を活かした体調管理、時間を意識した効率的な家事、急な対応に強い柔軟さなどがあります。
看護師としての経験が、家庭でも多くの場面で活かされます。
\効率的な家事分担・家事の負担軽減の記事はこちら!/
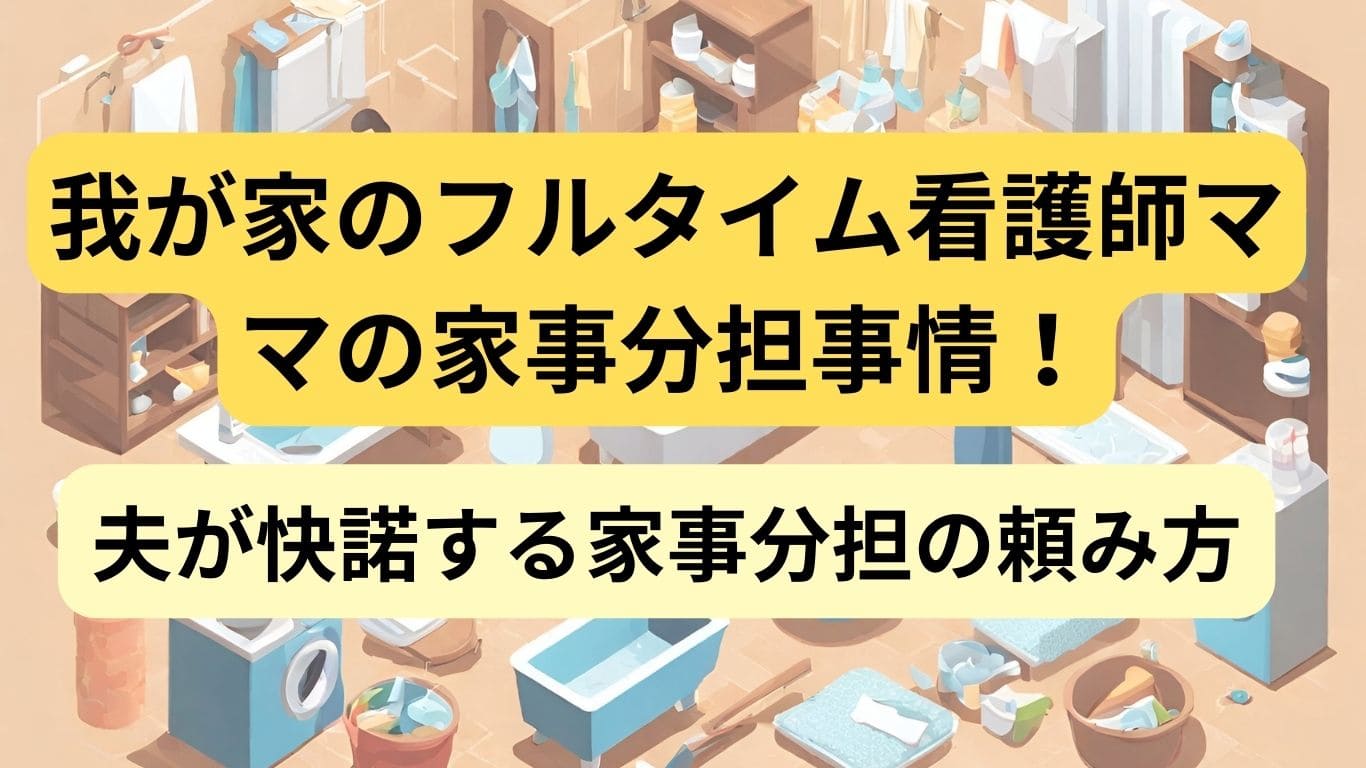
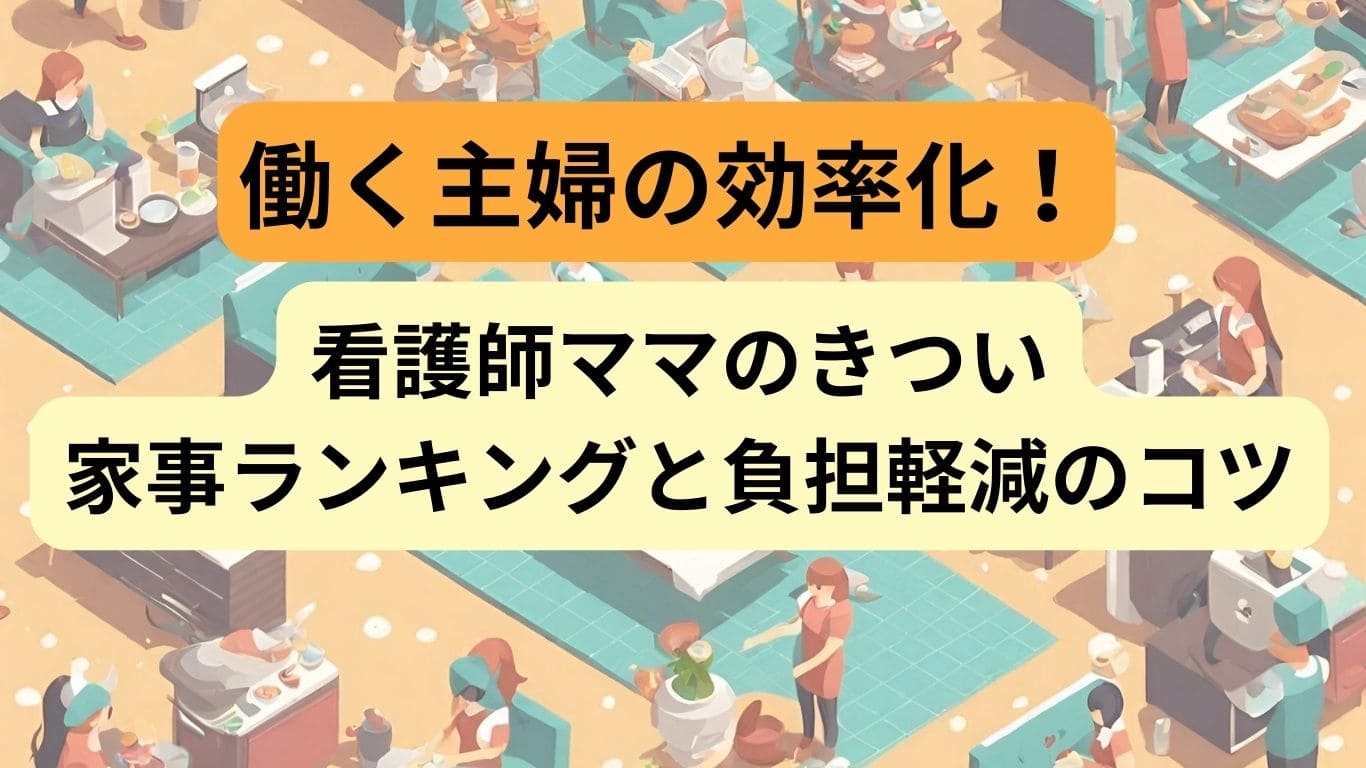
まとめ
看護師ママの毎日は、本当にハードです。
命と向き合う現場で気を張りつつ、家に帰れば子どもと向き合う日々。
「自分のことは後回し」になってしまうのも、仕方ないかもしれません。
でも、忘れないでほしいのは、完璧じゃなくても、十分頑張っているということ。
「今日はこれだけできたからOK」「明日はちょっと休もう」そんなふうに、自分自身をねぎらう言葉を持てることが、長く育児と仕事を続けるカギになります。
この記事で紹介した「あるある」に少しでも共感し、「自分だけじゃない」と感じてもらえたなら、それだけで価値があります。
頑張るあなたに、心からエールを。
“頑張りすぎない力”も、立派なスキルです。