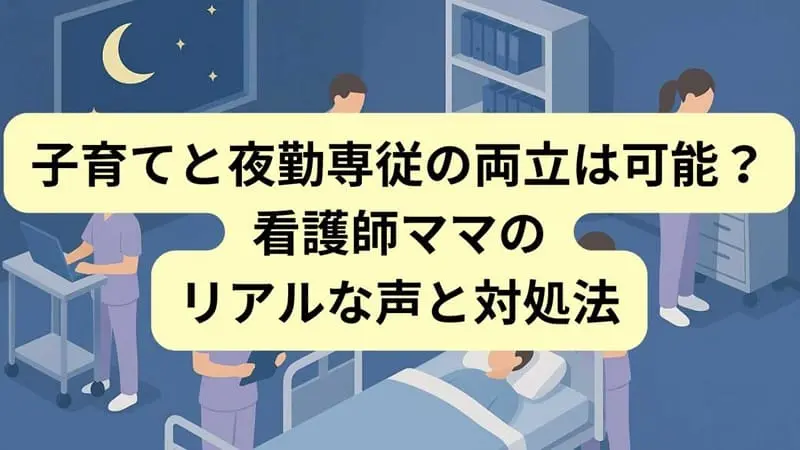夜勤専従の看護師として働きながら子育てを両立させることに、不安や悩みを感じているママは少なくありません。
夜間勤務による生活リズムのズレや育児との両立に伴うストレス、家族との連携など、さまざまな課題があります。
本記事では、実際に夜勤専従で働く看護師ママたちのリアルな声をもとに、よくある悩みとその具体的な対処法を紹介します。
限られた時間とエネルギーの中で、子育ても仕事も無理なく続けていくためのヒントを探してみましょう。
この記事でわかること
・夜勤専従で働く看護師ママのリアルな生活リズムと悩み
・生活リズムのズレや家族との連携に関する課題
・子どもへの影響と心理的ケアの工夫
・効率的な家事・育児のコツとサポート制度の活用方法
・夜勤育児を支えるアプリやツールの活用術
子育てと夜勤専従を両立する看護師ママのリアルな状況
子育てと夜勤専従を両立する看護師ママのリアルな状況についてお伝えします。
夜勤専従の勤務体制とは?
夜勤専従は、日勤を一切担当せず、夜間のみ連続して勤務するスタイルです。
勤務形態は病院ごとに異なりますが、一般的には「16時間夜勤+仮眠時間」「週3~4回の夜勤シフト」が中心です。
勤務間隔の調整や勉強会など昼間行事への参加難易度は高く、夜間業務の独特なリズムと責任感に慣れる必要があります。
子育てと両立する際、生活リズムの調整や家族の協力体制がポイントとなります。
夜勤専従の勤務形態や仮眠・休憩の取り方については、日本看護協会の「夜勤・交代制勤務ガイドライン」も参考になります。
安心して働くための制度設計として、ぜひご一読ください。
(参考:日本看護協会「夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」)
体験談
夜勤は夜18時から翌朝9時まで。
日中に仮眠を取りつつ、子どもが保育園に行っている間に体力の回復を図っています。
ただし、連続夜勤後の翌日はフルに休みでも、生活リズムの崩れを感じ、復帰が難しい時もありました。
\夜勤専従看護師の詳細はこちら!/
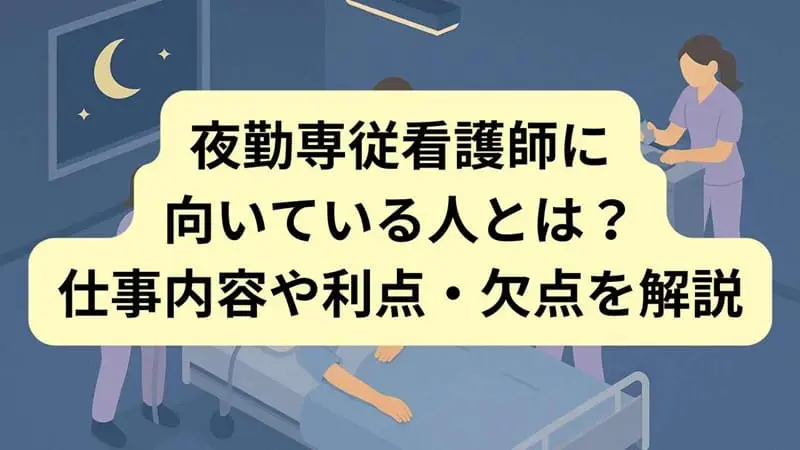
実際に働くママナースの1日(+α)のスケジュール
実際に働くママナースの1日のスケジュールとはどのようなものなのでしょうか。
夜勤(18:00–翌9:00)のある看護師ママの一日 (病院によってスケジュールに差があります)
| 時間帯 | 活動内容 |
|---|---|
| 06:00–07:30 | 起床・朝食準備・子どもの送り出し |
| 07:30–12:00 | 家事・仮眠・子どもとの遊びや送り迎え |
| 12:00–14:00 | 昼食・仮眠 |
| 14:00–16:00 | 日中の買い出し・書類や家計整理など |
| 16:00–17:00 | 仮眠の調整(夜勤用) |
| 17:00–18:00 | 夕飯準備・子どもとのコミュニケーション |
| 18:00–翌9:00 | 夜勤勤務 |
| 翌9:00–10:00 | 仮眠・帰宅 |
| 10:00–12:00 | 入浴・軽い家事・休養 |
体験談
毎回の夜勤でこのリズムを回すのが最初は大変でした。
仮眠と育児時間のギリギリを見極めつつ、子どもから“おはよう”と言ってもらえる時間を確保したいと工夫してきました。
特に夕方の1時間は“ママ時間”として大切にし、子どもが笑顔で送り出せるよう努めています。
仕事・育児・睡眠のバランスがどう変わるのか?
夜勤中心の生活になると、日中に長時間の仮眠が必須となり、子育てとの接触可能時間が限られてしまいます。
朝晩の時間帯は比較的濃密に過ごせる一方、日中の活動時間は削られがち。
睡眠の断片化により体調や精神の不安定さが増しやすくなります。
さらに、子どもが不規則な生活リズムに適応しても、家庭内でのケア体制に負担が生じ、連携のズレがストレスの一因になります。
体験談
夜勤に入る前後は、子どもとの濃い時間を意識しますが、日中の“普通の公園遊び”ができないことに罪悪感を覚える日も。
睡眠も3〜4回に分けざるを得ず、集中力が続かない時期もありました。
でも、夜勤明けに“ママ大好き!”と言われる瞬間には、また頑張れます。
子育てと夜勤専従の両立における看護師ママの最大の悩み
生活リズムのズレによるストレス
夜勤と子育ての両立で最も大きな課題の一つが、生活リズムのズレによる心身への負担です。
夜間に働き、昼間に仮眠を取るというサイクルは、体内時計を大きく狂わせ、慢性的な疲労感を引き起こします。
特に小さなお子さんがいる場合は、昼寝や食事の時間が親と合わず、日中に頻繁に中断されることで十分な休息が取れません。
加えて、家庭内での音や動きによって眠りが浅くなりがちで、睡眠不足からくるイライラや集中力の低下も悩みの種となります。
体験談
夜勤明けはすぐに仮眠を取りたいのですが、子どもの声や家事の音でどうしても浅い眠りになってしまいます。
休めないまま次の勤務日を迎えると、気力も体力も限界で…。
それでも、“お母さん、遊ぼう!”と無邪気に笑う子どもを見ると、なんとか笑顔で向き合いたいと自分を奮い立たせます。
家族・パートナーとの協力体制の難しさ
夜勤専従で子育てをするには、家族の協力が不可欠です。
しかし、実際には「パートナーの勤務時間が合わない」「祖父母が遠方にいて頼れない」など、支援が受けにくい環境にあるママも多いのが現状です。
特に、夜勤明けで眠っている間の育児や、夜勤前に子どもを保育園へ送り出すタイミングに、誰かの助けが必要となる場面が増えます。
協力が得られないと、看護業務だけでなく家庭でも「ワンオペ状態」が常態化し、精神的な孤立感や責任の重圧を感じやすくなります。
体験談
夫は日勤の仕事で、私の夜勤スケジュールには対応できず、結局すべて一人でこなす日も少なくありませんでした。
夜勤前に寝かしつけを済ませてから出勤し、夜中に何度も“ママは?”と泣かれるのがつらくて…。
思い切って夫と話し合い、送り迎えだけでもお願いしたら、かなり気持ちが軽くなりました。
 看護師ママ
看護師ママ子どもの送り迎えしてもらえる方がいないと夜勤専従は厳しいですね…。
 飯野
飯野そうですね。けれども、共働きであれば、やはり家事子育て分担はしたいですね。ワンオペは負担が大きすぎますから。
\夫との子育て・家事分担術の記事はこちら!/
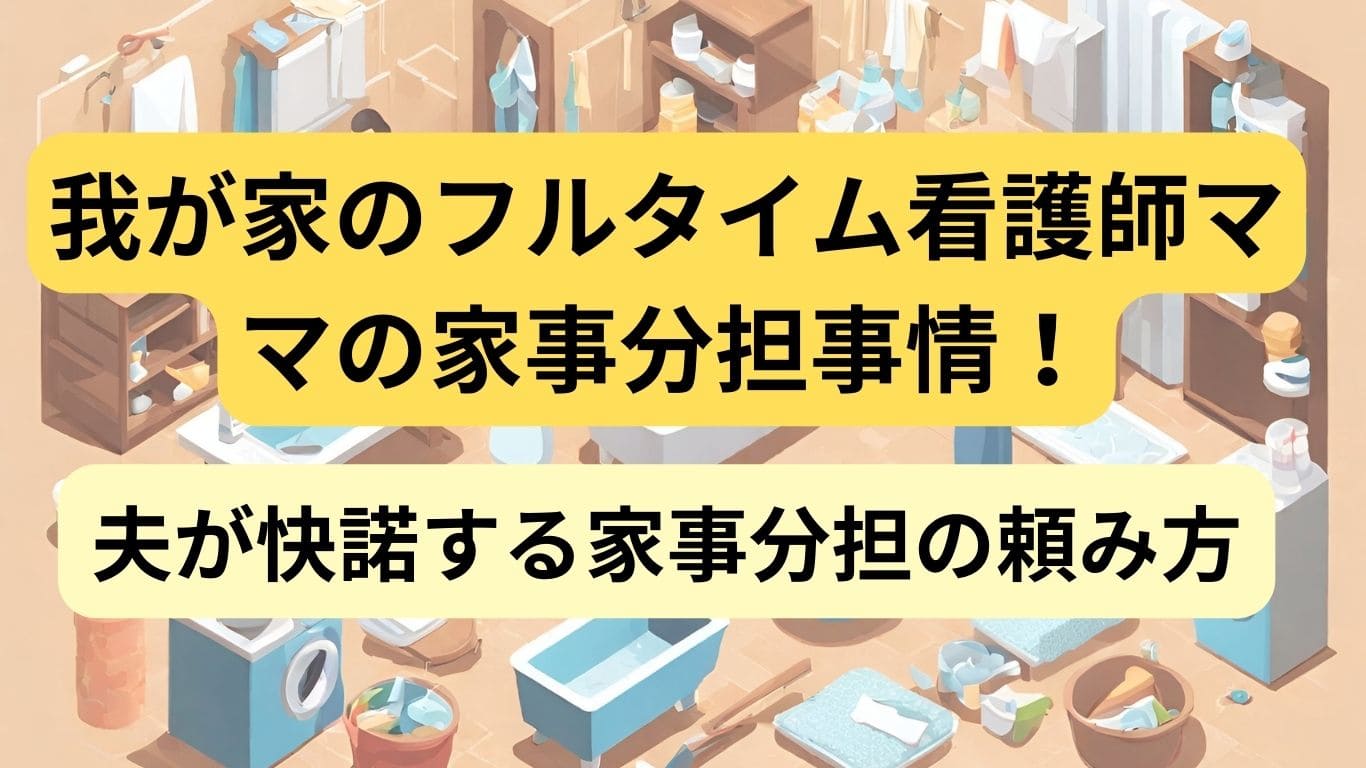
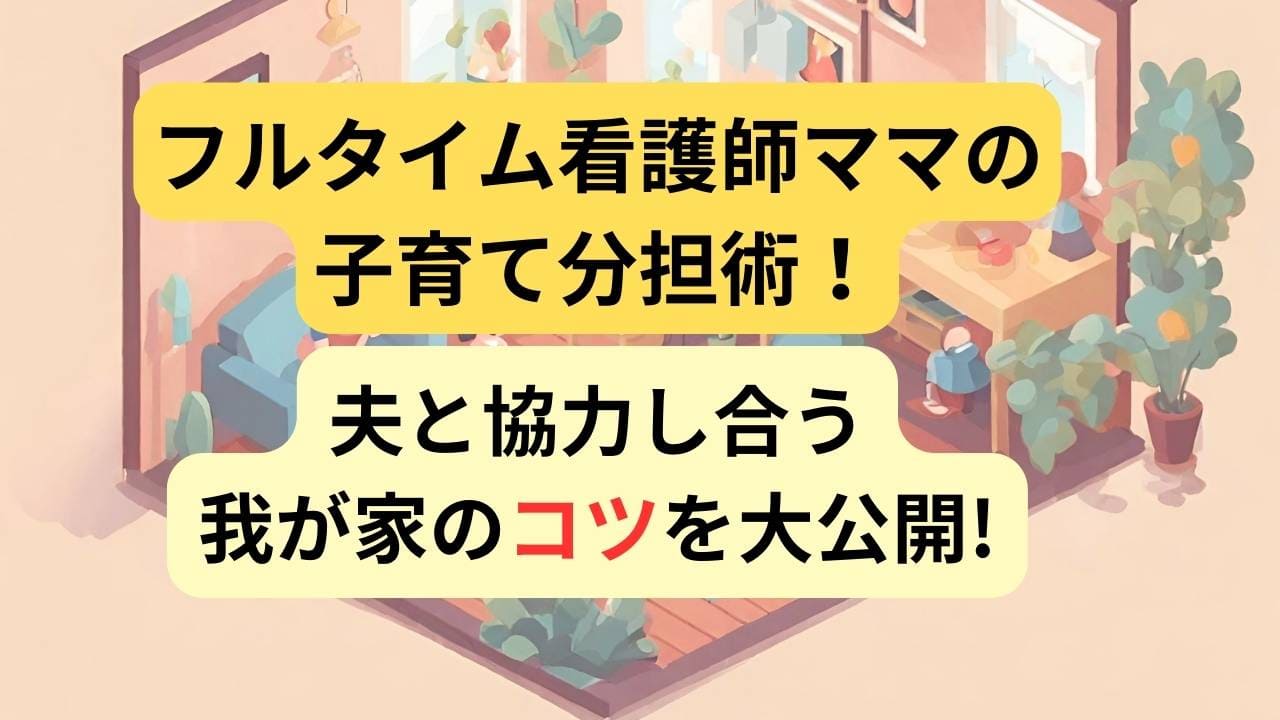
子どもの不安や負担感への対応
夜勤専従で働くママにとって、子どもに与える心理的影響も大きな懸念です。
特に未就学児の場合、「夜にママがいない」という状況に強い不安を抱くことがあり、不眠や情緒不安定といった反応が現れることもあります。
また、急な夜間の病気やケガの際にママが不在であると、子どもだけでなく預け先の大人にも大きな負担がかかります。
そのため、夜勤前に子どもへの声かけや日常の安心感の積み重ね、万が一の対応を事前に共有するなどの工夫が必要です。
体験談
子どもが3歳のとき、“ママ、夜いないの嫌だ”と何度も泣かれてしまい、心が痛みました。
それ以来、夜勤の前には必ず“明日は先生と一緒に遊んでるね”と説明し、安心させるようにしました。
帰宅後にはぎゅっと抱きしめて、どんなに眠くても“ママ戻ったよ”と伝えるようにしています。
夜勤専従看護師ママが実践する効果的な対処法
夜勤専従看護師ママが実践する効果的な対処法についてお知らせします。
時短&効率的な家事・育児術
夜勤専従ママが子育てと家事を両立するには、効率的な時間の使い方が重要。
代表的な工夫には、食材宅配やネットスーパーの活用、週末の作り置き、掃除ロボットや乾燥機付き洗濯機の導入があります。
また、朝の時間帯を「家事タイム」と決めて集中することで、日中の仮眠時間を確保しやすくなります。
子どもの着替えや荷物の準備も前日のうちに済ませておくことで、バタバタ感が減り、精神的にも余裕を持てるようになります。
小さな積み重ねが、大きな負担軽減につながるのです。
体験談
以前は毎日夕食を一から作っていましたが、夜勤のある週は作り置きを活用するようにしました。
味噌汁も冷凍保存し、朝チンするだけに。
子どもの保育園の準備も夜に済ませ、朝は笑顔で送り出せるようになったのがうれしい変化でした。
\家事負担軽減のコツの記事はこちら!/
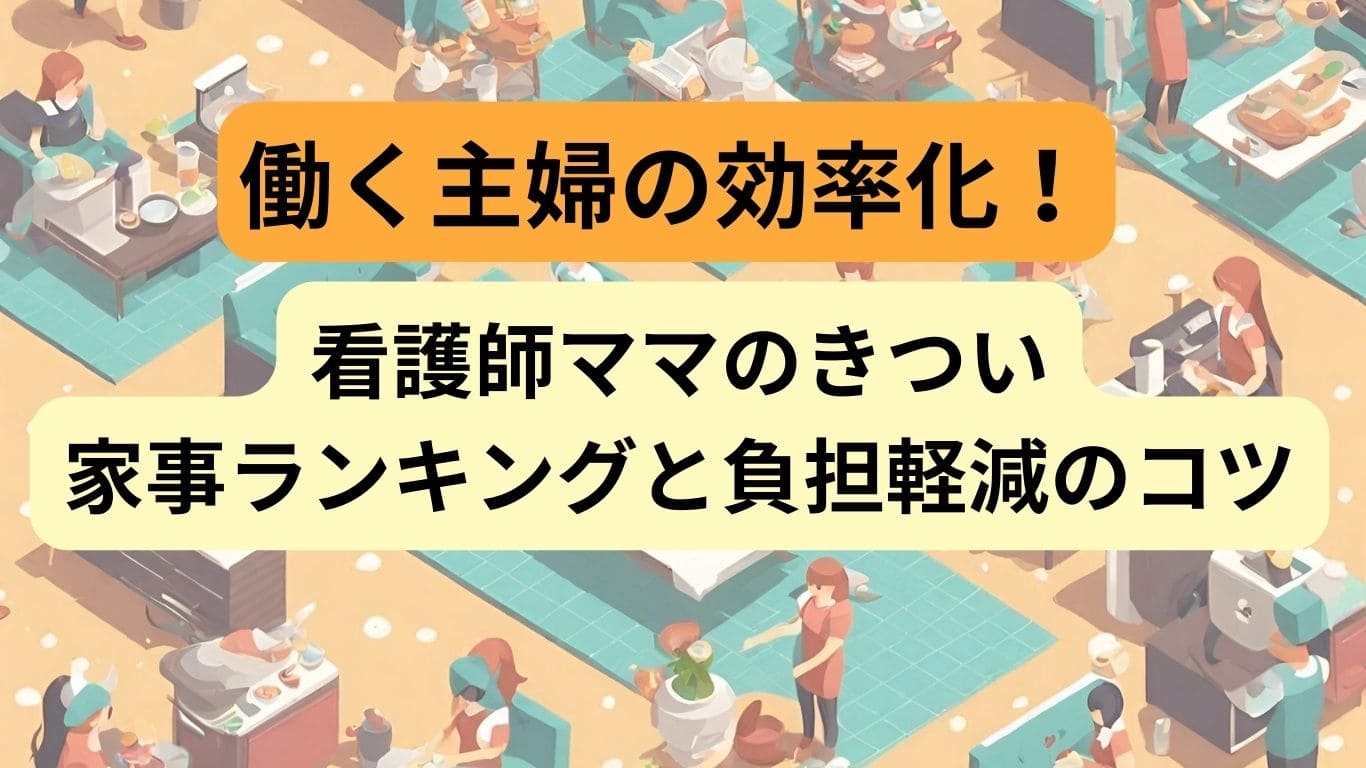
保育園・頼れる人との連携のコツ
夜勤ママにとって、保育園の選び方と連携体制は非常に重要です。
まずは24時間保育や深夜保育に対応した園を検討し、自分のシフトに合う施設を選びましょう。
また、ファミリーサポートセンターやシッターサービスの併用も有効です。
園としっかり連絡を取り、急な夜勤変更時の対応をあらかじめ確認しておくことで、トラブルを未然に防げます。
さらに、保育士と定期的にコミュニケーションを取り、子どもの様子や変化を把握しておくことも、安心して働くために欠かせません。
体験談
うちは夜間保育のある園を選びましたが、それでも体調不良などで預けられない日もあります。
そんなとき、近所のファミサポさんに助けられました。
登録しておくだけで“いざ”という時にお願いできるので、精神的にも余裕が持てました。
自己ケア・メンタルヘルスの維持法
夜勤で体力を消耗しやすいママナースにとって、自己ケアとメンタルの安定は重要な課題です。
まず、こまめな仮眠と睡眠の質向上が基本。
遮光カーテンや耳栓、スマホ断ちなどで快適な睡眠環境を整えることが推奨されます。
さらに、ストレッチや軽い運動、好きな香りを取り入れたアロマ、短時間のカフェタイムなど、小さなリラックス習慣も効果的です。
また、同じ立場のママ友と悩みを共有することが、孤独感を和らげる支えになります。
自分を大切にする意識が、育児や仕事への前向きなエネルギーにつながります。
体験談
以前は“母親だから頑張らないと”と無理をしていましたが、限界を感じたときにカウンセリングを受けてみたら、気持ちがすごく軽くなりました。
今は子どもが保育園に行っている間にカフェでコーヒーを飲むのが私の癒し。
ママでも一人の時間は大切ですね。
 看護師ママ
看護師ママカウンセリングは「精神を病んでいる」とイメージがあって、なかなか敷居が高いイメージがあります…。
 飯野
飯野昔はそういうイメージがありましたね。今は、そんなことはないので、もやもやしたら気軽に利用してみてくださいね。
夜勤専従×子育てママにおすすめのサポート制度
夜勤専従子育てママにおすすめのサポート制度についてご紹介します。
病院が提供する福利厚生とその活用法
多くの病院では、子育てをしながら働く職員に向けた福利厚生制度が整備されています。
代表的なものに、24時間対応の院内保育所、夜勤免除制度、時短勤務制度などがあります。
院内保育は夜勤時にも預けられるため、夜勤専従のママには心強い味方です。
また、育児に理解のある上司のもとで勤務シフトの調整が可能であれば、突発的な子どもの病気にも柔軟に対応できます。
これらの制度を最大限活用するためには、事前に就業規則を確認し、自分のライフスタイルに合った相談を行うことが重要です。
体験談
私の職場には24時間の院内保育があり、夜勤中も安心して子どもを預けられます。
保育士さんが看護の現場にも理解があって、“お母さん、今が一番大変な時期よね”と声をかけてくれるのが救いでした。
制度を知らないと損なので、就職前にしっかり調べることをおすすめします。
夜間保育やファミリー・サポート・センターなど、自治体が提供する子育て支援制度の最新情報は、こども家庭庁の「子ども・子育て支援新制度」の資料から確認できます。
緊急時の備えとしてもご活用ください。
(参考:こども家庭庁「子ども・子育て支援新制度」)
自治体や地域の支援サービス
病院の支援制度に加え、自治体が提供する子育て支援サービスも大いに活用したいポイントです。
具体的には、夜間・休日の一時保育、ファミリー・サポート・センターによる送迎や預かり支援、母子家庭・共働き世帯向けの保育補助などがあります。
地域によっては、保育施設と連携した訪問型保育や、保健センターによる育児相談会も開催されています。
これらの情報は市区町村の子育て支援窓口やWebサイトで簡単に確認できますので、定期的にチェックすることが大切です。
体験談
うちの自治体には、夜間の一時預かりに対応している施設があり、本当に助かりました。
急な夜勤が入ったときでも、事前登録していたことでスムーズに利用できました。
保健センターの育児相談も定期的に利用しています。地域の力って本当にありがたいですね。
育児と仕事に役立つアプリ・ツール紹介
忙しいママナースの強い味方が、育児や家事、仕事の効率化を支援するアプリやデジタルツールです。
たとえば、家族間のスケジュール共有には「TimeTree」、育児記録管理には「ぴよログ」、買い物リストの共有には「Google Keep」などが便利です。
また、看護業務の記録や情報収集には「ナースプラス」や「看護roo!」といった専門アプリも活用されています。
さらに、睡眠の質を高めるための「Sleep Cycle」などのヘルスケアアプリもおすすめ。
これらのツールを上手に取り入れることで、少しでも負担を減らし、家庭と仕事のバランスを取りやすくなります。
体験談
スケジュールの共有はTimeTreeで夫と連携しています。
夜勤の日は子どもの送り迎えや夕飯準備を分担しやすくなりました。
ぴよログは育児日記にもなるので、見返すと“あの時も頑張ってたな”って励みになります。
スマホ一つでここまで支えられるなんて、便利な時代ですよね。
子育てと夜勤専従の両立に関するよくある質問
子育てと夜勤専従の両立に関するよくある質問についてお答えします。
まとめ
夜勤専従で働きながら子育てをすることは、簡単なことではありません。
生活リズムのズレや家族の協力体制の確保、子どもの心のケアなど、多くの課題と向き合う必要があります。
しかし、その一方で、効率的な家事術や外部支援の活用、ママ自身のメンタルケアといった工夫次第で、無理なく両立する道も確かに存在します。
今回ご紹介した体験談や対処法は、同じ立場で悩む看護師ママたちのリアルな声です。
「私だけが大変なんじゃない」と気づくだけでも、心はぐっと軽くなるはず。
まずは自分と家族に合った方法を見つけ、無理なく前向きに、日々の育児と仕事を両立していきましょう。
あなたの頑張りは、必ず誰かの力になっています。