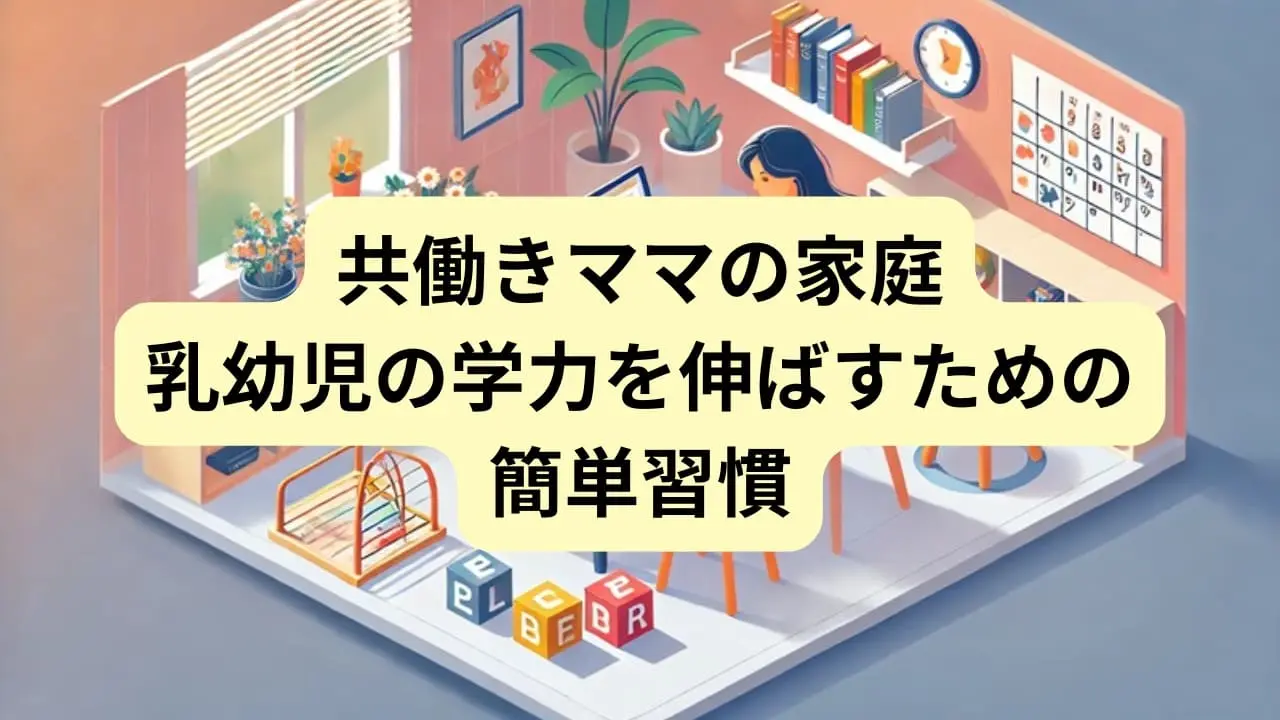共働きで忙しい中でも、乳幼児の学力を無理なく伸ばす習慣があることをご存知ですか?
「乳幼児期に必要な学び」は特別な教材や高額な塾がなくても十分に身につけることができます。
この記事では、日々の生活の中で取り入れられる知育習慣について解説していきます。
ひとつでも参考になることがあれば幸いです。
この記事でわかること
・「共働き 知育」「乳幼児 学力 伸ばす」などの検索意図に応える情報
・日常生活で実践できる乳幼児の学力アップ習慣3選
・看護師の専門知識から見る、成長ホルモンと睡眠の重要性
・子どもの思考力・語彙力・集中力を高める親子コミュニケーション術
・ワンオペでも大丈夫!忙しくても無理なくできる知育の工夫
働くママの子育て!乳幼児期に学力を伸ばすために必要な3つの習慣
乳幼児の学力を伸ばすには、以下の3つの習慣が重要です。
①語彙を増やすための「会話の習慣」
語彙力を養うためには、「会話の習慣」がおすすめです。
✅ 実践方法
・実況中継のように話す:「今、お野菜を切ってるよ。にんじんがオレンジ色でキレイだね。」
・子どもの言葉を広げる:「ワンワン!」→「そうだね、大きな犬だね。」
・本の読み聞かせを習慣にする(1日5分でもOK!)
言葉の発達は、乳幼児期の学力向上に直結します。
ベネッセが2015年に行った「幼児期から小学1年生への縦断調査」では、親子で読み聞かせやことば遊びを頻繁に行う家庭の子どもは、5歳時点で「学びに向かう力」や「文字・数・思考能力」が高いことが明らかにされています。
(参考:ベネッセ「母親の就労有無に関わらず親子で“知的なやりとり遊び”をよくするほうが5歳児の「学びに向かう力」は高い」)
忙しくなるとついつい会話をおろそかにしがちになってしまいますが、お話すればするほど子どもたちはぐんぐん言葉を覚えていきます。
言葉がわかると、周囲の会話がわかるようになってきます。
ゆっくりじっくり、日中に子どもとの時間が取れればいいのですが、共働きだとなかなかその時間も難しいもの。
家事の時、お風呂の時、食事の時、車に乗る時、いつでもどこでも会話を組み込むことをおすすめします。
子どもの学習能力を高めたいという後輩の体験談についてご紹介します。
体験談
私は1歳の娘を育てながらフルタイムで働いています。
娘が生後6か月を過ぎたころから、できるだけたくさん話しかけることを意識しました。
最初は「今日はいい天気だね」「お洋服かわいいね」などの簡単な言葉でしたが、1歳になるころには「お花がきれいだね。
これはチューリップっていうんだよ」と、より具体的な会話を心がけるようにしました。
良かったことは、娘の言葉の発達が早かったことです。
1歳半ごろには「ワンワン、かわいい!」と2語文を話せるようになり、2歳を迎えるころには「ママ、お茶ちょうだい」と会話が成立するようになりました。
一方で苦労したのは、忙しい時にじっくり話しかける時間が取れないことです。
そこで、「料理中でも実況中継のように話す」「お風呂の時間に今日あったことを話す」など、生活の中に話す機会を組み込みました。
話しかけることに特別な準備はいらないと気づいてからは、無理なく続けられるようになりました。
② 自分で考える力を育てる「問いかけ習慣」
自分で考える力を育てるためには「問いかけ習慣」が効果的です。
✅ 実践方法
・「どうしてそう思ったの?」と質問する:「この積み木はどうして倒れたのかな?」
・選択肢を与える:「赤い服と青い服、どっちを着たい?」
・親も一緒に考える:「この動物、どこに住んでいるんだろうね?」
学力の高い子どもほど、日常生活の中で「なぜ?」「どうして?」と考える機会が多いといわれています。
身近にもいませんでしたか?
私の周囲にはちらほらといました。
何でもかんでも疑問を持つので、面倒になって無難に避けてしまう大人や同級生などもいましたが、親御さんが優しく根気よく会話を導いて、疑問を解消していたのをよく覚えてします。
わからないことは親子で調べたり直接見に行ったりなどしていました。
ちょっと動作に鈍いところのある子もいましたが、数年後、県トップ校に余裕が合格していました。
疑問を持つこと、それについて考えることは、勉強に対してだけではありませんので、進路に関してもいかんなく発揮して、自分で調べ、解決しながら方向を決めていました。
自分で考えて未来を切り開けるようになって欲しい方も多いのではないでしょうか。
放っておいても自分で疑問を立ち上げる子どもももちろんいますが、たとえそうでない子でも考える力は養えます。
親が意識的に「考える問いかけ」をすることで、子どもの思考力を養うことができるのです。
ぜひ日常に取り入れてみてくださいね。
以下は実践した方の体験談です。
体験談
私には3歳になる息子がいます。
息子は好奇心旺盛で、「これ何?」「どうして?」と質問が多いタイプでした。
私自身、答えをすぐに教えてしまいがちだったのですが、子どもの思考力を育てるために「すぐに答えを言わない」ことを意識するようにしました。
例えば、公園でアリを見つけたとき。「アリさん何してるの?」と聞かれたら、「何してると思う?」と質問を返しました。
すると息子は「ご飯食べてるのかな?」と自分で考え始めました。
そこから「どこからご飯を持ってきたのかな?」と会話を広げることで、自然と考える習慣がついたようです。
ただ、忙しい時に「なんで?」攻撃を受けると、つい「後でね」と流してしまうこともありました。
そんなときは「今は忙しいけど、お風呂のときに一緒に考えようね」と伝えることで、子どもの好奇心を無視せずにすみました。
「考える時間」を生活の中に組み込むのが、無理なく続けるコツだと感じています。
③ 生活リズムを整える「学びの習慣」
生活リズムを整えて集中力を養うことをおすすめします。
✅ 実践方法
・決まった時間に起床・就寝する(6~7時起床、20時就寝が理想)
・朝ごはんをしっかり食べる(脳の活性化につながる)
・寝る前のスマホ・テレビは控える(睡眠の質を下げないため)
乳幼児期の脳は、「規則正しい生活」が発達に大きく影響します。
特に、早寝早起きや食事のリズムを整えることが、集中力や学習意欲の向上につながります。
「規則正しい生活習慣が、幼児期の学習意欲や注意力を高める」
(出典:文部科学省「子どもの生活リズムと学習」)
とはいえ、共働きだと20時就寝にはなかなか間に合わないこともあります。
そんな時は、夫婦で協力して、遅くとも21時には就寝できるようにすると良いですね。
以下の体験談は就寝時間に四苦八苦していた後輩のものです。
体験談
フルタイム共働きの我が家では、毎日の生活リズムを整えるのが最大の課題でした。
息子が1歳半のころ、仕事の都合で夕食が遅くなり、寝る時間が22時を過ぎることが多くなってしまいました。
そのせいか、朝起きるのが遅くなり、保育園でも午前中はぼーっとしていることが増えてしまったのです。
そこで、我が家では「絶対に21時までに寝るルール」を決めました。
そのために、夕食を18時30分までに終わらせるようにし、19時からはテレビやスマホを見せないようにしました。
最初は寝る時間を早めるのに苦労しましたが、1週間ほど続けると自然とリズムが整い、朝もスッキリ起きられるようになりました。
その結果、息子の集中力がアップし、絵本の読み聞かせの時間も増えました。
以前はすぐに飽きてしまっていたのに、じっくり話を聞けるようになったのです。
生活リズムを整えることが、学びの土台になると実感しました。
看護師が伝えたい!乳幼児の脳と睡眠の関係
看護師として長年子どもの発達を間近に見てきましたが、「睡眠と脳の成長の関係」は非常に密接です。
実際、乳幼児の脳は寝ている間に記憶を整理し、学習した内容を定着させています。
看護師として特に伝えたいのは、「良い睡眠がとれないと成長ホルモンの分泌が妨げられる」という事実。
睡眠の質の大切さです。
生活リズムを整え、就寝時刻を毎日同じ時間にするよう心掛けると良いですね。
(参考:日本睡眠学会総合専門医 阪野勝久「睡眠の質と深い関係にある成長ホルモンの知識」)
成長ホルモンの分泌が妨げられると、身長の伸びが遅くなり、同年齢の子どもと比べて小柄になることがあります。
また、筋肉の発達も遅れ、骨の成長も影響を受けてしまいます。
睡眠不足が続くと、情緒の不安定さや注意力の低下が見られることもあります。
乳幼児は12~15時間ほどの睡眠を必要としますから、忙しい日でも「21時までの就寝」を目指すと、生活・睡眠の習慣が無理なくまわりやすいかと思います。
(参考:たまひよ「子どもの遅寝は絶対にダメ⁉ 成長ホルモンのためにしたいことを米国IMPI公認・乳幼児睡眠コンサルタントにきいてみた」)
働くママの子育て!子どもが自分で学ぶ力を育てるコツ
子どもが自分で学ぶ力を育てるコツは何なのでしょうか。
「親が何でも教える」のではなく、「子どもが自ら学ぶ環境を作る」ことが大切です。
医療現場から見た“学びたくなる子”の共通点とは?
私が勤務する病院の小児外来でも、観察していて「学びたくなる子」と「無関心になりやすい子」には明確な違いがあります。
共通しているのは、「質問を受け止めてもらえる経験が多い」子どもは、知的好奇心がとても強いこと。
医療的には、「興味→質問→承認→好奇心強化」という流れが神経回路を刺激し、認知発達にプラスに働きます。
親が「また質問?」とあしらわず、「一緒に考えよう」と向き合うだけで、将来的な学力差につながることも珍しくありません。
ぜひ「学びたくなる子」の環境をつくっていきましょう。
(参考:あづま幼稚園「幼児教育の重要性と最新トレンド 子どもの未来を育むために知っておくべきこと」)
① 興味を引き出す環境づくり
子どもは「好きなこと」には自然と没頭します。
興味を持つきっかけを増やすことが、自主的な学びにつながります。
✅ 具体例
・身近なものを使って学ぶ(料理で数を数える、買い物で計算する)
・いろいろなジャンルの絵本をそろえる(動物、乗り物、食べ物など)
・「なぜ?」を大切にする(一緒に図鑑で調べてみる)
「好きなこと」ができるということは集中力を養い、考えることを学ぶのにはとてもよいチャンス。
うまく活用したいですね。
体験談
私には4歳の娘がいます。
小さいころから「お絵描き」や「折り紙」が好きだったのですが、知育という意識はあまりなく、遊びの延長として楽しんでいました。
しかし、ある日、娘が「どうして虹は7色なの?」と聞いてきたことをきっかけに、子どもの「好き」をもっと伸ばしてあげたいと考えるようになりました。
そこで、娘が興味を持ちそうなものを生活の中に取り入れるようにしました。
例えば、図鑑や絵本をリビングに置く、動物園や科学館に連れていく、折り紙や工作を増やすなど、環境を整えていきました。
すると、「このお花の名前は何?」「星はどうやって光るの?」など、さらに新しい疑問が増えていきました。
一方で、私自身が理科や図鑑に詳しくなかったため、すぐに答えられないことも多々ありました。
でも、「ママも知らないなあ。一緒に調べてみよう!」と言って、スマホで調べたり、図鑑で探したりすることで、娘も「わからないことは自分で調べる」という習慣がついたように思います。
忙しくてじっくり付き合えない日もありましたが、そんなときは「明日の夜、一緒に調べようね」と約束することで、娘の探求心を大事にするようにしました。
「興味を広げる環境を作ること」こそが、子どもが自ら学ぶ力を育てる第一歩だと実感しました。
② 「できた!」を増やして自信をつける
子どもが学び続けるには、「楽しい!」「できた!」という成功体験が必要です。
✅ 具体例
・小さな成功体験を増やす:「ボタンを自分で留められたね!」
・結果よりプロセスを褒める:「頑張って考えたね!」
・子どもに選択肢を与える:「どっちの絵本を読みたい?」
「できた!」という喜びは子どもだけでなく大人もとても嬉しいものですね。
その喜びが次の行動につながります。逆に「できた!」と感じられないと、やる気も出ませんし、自信もつきません。
子どもが自発的に学ぶためには「できた!」で自信をつけるという成功体験がとても重要です。
以下は成功体験について意識し、子どもへのアプローチに成功した方の体験談です。
体験談
私の息子(5歳)は、もともと慎重な性格で、新しいことに挑戦するのが苦手でした。
例えば、ブロック遊びをしているときに「うまく作れない」と言ってすぐにやめてしまうことが多かったのです。
そこで、「小さな成功体験を増やす」ことを意識するようにしました。
まずは、簡単なことでも「できた!」を感じられるようにすることからスタートしました。
例えば、ブロックなら「ここまで作れたね!すごい!」と途中経過を褒めたり、「この部分はどうしたらうまくいくかな?」と一緒に考えたりしました。
また、洋服のボタンを留めたり、ハサミを使ったりするなど、生活の中でも「ちょっとした成功」を見つけて褒めるようにしました。
すると、少しずつ「やってみよう!」という気持ちが芽生え、今では「ママ見て!こんなの作ったよ!」と自分から挑戦する姿が増えてきました。
最初は「できない!」とすぐ諦めていた息子が、「もう一回やってみる!」と言うようになったことが、本当に嬉しかったです。
私自身、つい「もっとこうしたらいいよ」と口を出してしまいがちでしたが、「結果よりも過程を認める」ことが大切だと学びました。
子どもが自信を持って学ぶためには、「できた!」を積み重ねる環境を作ることが大事なのだと実感しています。
知育は特別なことをしなくてもOK!日常生活で学ぶ方法
知育は日常生活で学べます。
もちろん、数ある習い事に行くというのも新しい環境としては良いものです。
ただ、学習は積み重ねが大事なので、日常の習慣にこまめに取り入れるととても効果が高いのです。
私の家庭では、夫婦ともにフルタイムで働いているため、子どものために特別な知育時間を確保するのは難しい状況でした。
そこで、「日常生活の中で学びの時間を作る」という方法を試してみることにしました。
例:お買い物
例えば、買い物のときに「りんごを3つ取ってきて」とお願いすることで、自然に数を数える練習ができました。
最初は「1、2、…あれ?」と途中で迷っていた娘も、繰り返すうちにスムーズに数えられるようになりました。
また、料理をしながら「このトマトは丸いね」「お塩をちょっと入れてみよう」と形や量を意識させることで、楽しく学べるようになりました。
特に効果を感じたのは、お風呂の時間でした。
例:お風呂
「このお湯は何色かな?」「シャワーのお水は上から落ちるね」と話しかけることで、「言葉の習得」や「考える力」が自然と身についているようでした。
また、寝る前に絵本を読むことも習慣にしていましたが、「これは何色?」「次はどうなると思う?」と質問を交えることで、理解力がぐんと伸びたように感じました。
忙しい中でも「知育を特別な時間にしなくていい」と思えたことで、無理なく続けられるようになりました。
子どもにとっては、「学ぶこと」そのものが遊びになると気づいたことが、私にとっても大きな収穫でした。
“生活習慣×脳科学”から見た知育のポイント
看護の知見からお伝えすると、乳幼児期の脳は「環境の変化」「繰り返しの刺激」「五感の体験」によって活性化されます。
たとえば、買い物や料理といった日常体験は、“脳にとっては最高のトレーニング”。
これは専門的に言うと、「実行機能(ワーキングメモリ・感情制御・集中力)」を養う土台にもなります。
意識して五感(見る・聞く・触る・嗅ぐ・味わう)を使う活動を取り入れていくことが、将来的な思考力の強化につながります。
(参考:林 隆博 (西焼津こどもクリニック 院長)「早期教育のポイントは社会脳と共生脳」)
よくある質問(FAQ)~共働き家庭での知育を無理なく続けるには?
共働き家庭での知育を無理なく続けるためのよくある質問についてまとめました。
\子育て分担術の記事はこちら!/
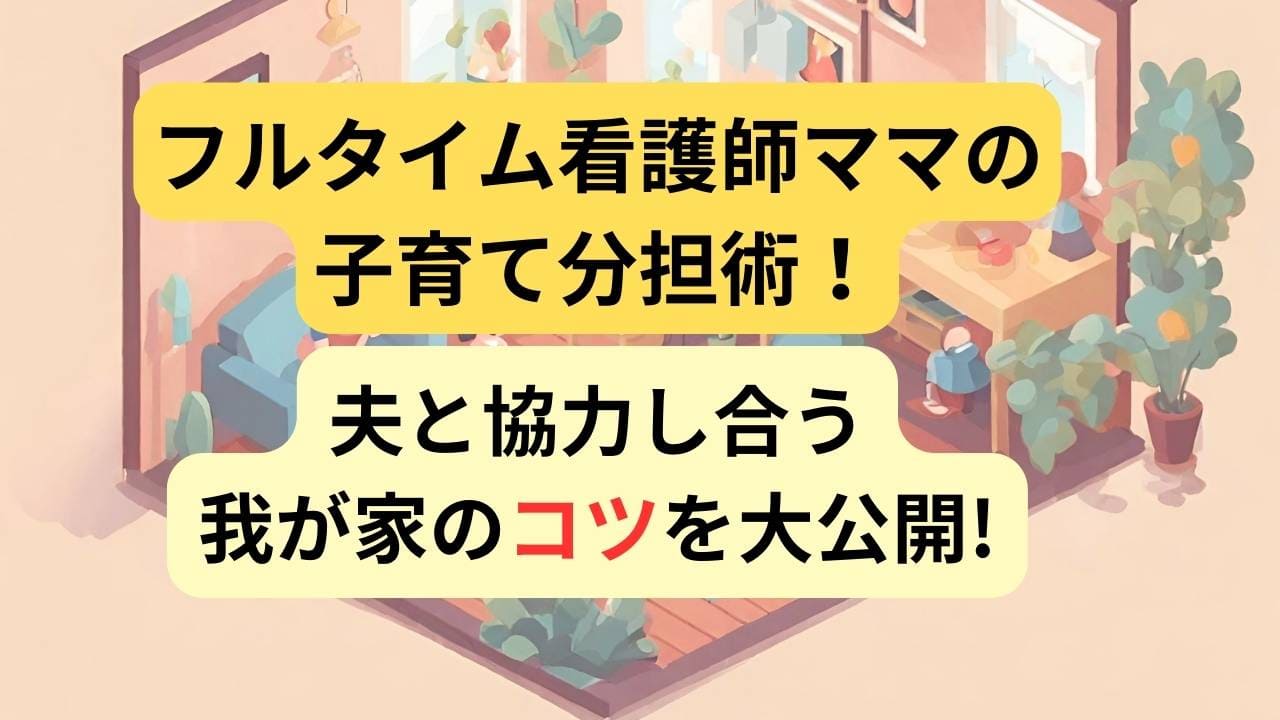
\小学生の学力を伸ばす記事はこちら!/
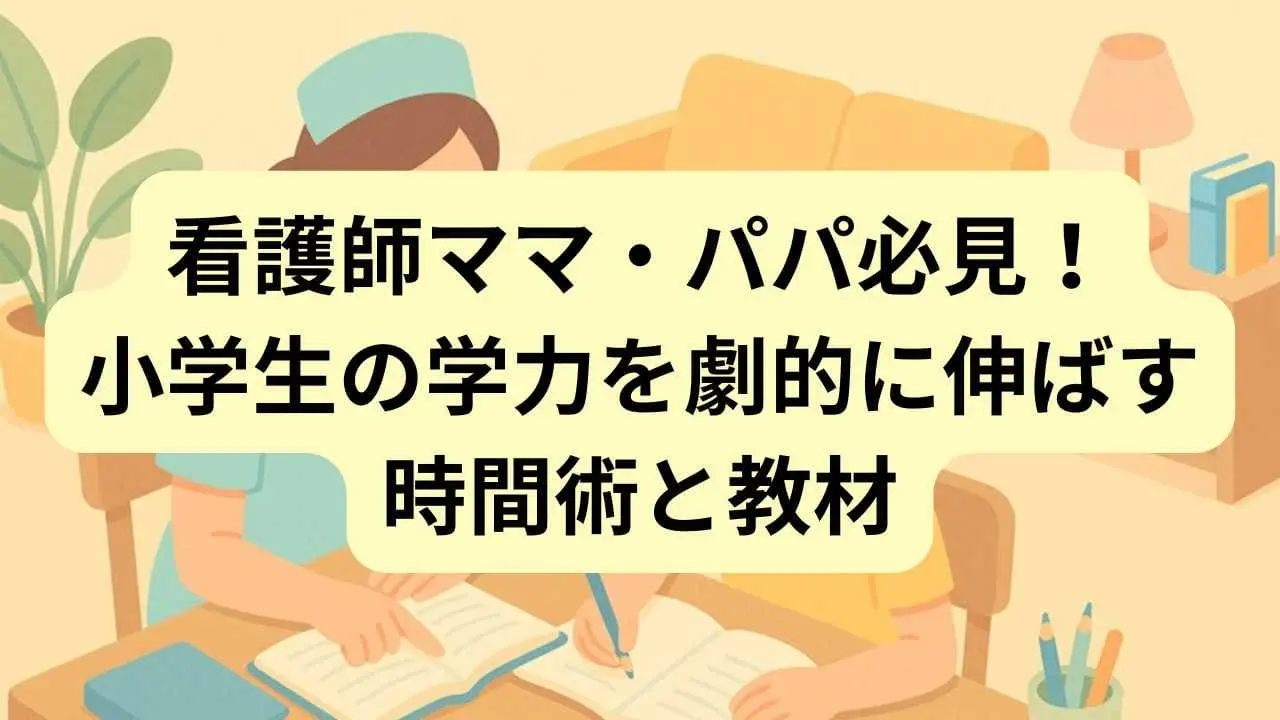
まとめ
共働きのママやパパでも、乳幼児の学力を伸ばすことは十分に可能です。
特別な教材や時間を用意しなくても、日常の会話や問いかけ、生活リズムの工夫だけで知育効果はしっかり得られます。
「おはよう」「これは何かな?」といった声かけは語彙力を育み、問いかけによって思考力を伸ばすことができます。
また、買い物やお風呂など日常の場面を活用すれば、知育を“特別なこと”ではなく、“暮らしの一部”として自然に取り入れることができます。
忙しい中でも、「できた!」という成功体験を増やし、子どもが自分から学びたくなる環境を整えることが、将来の学力につながる第一歩です。